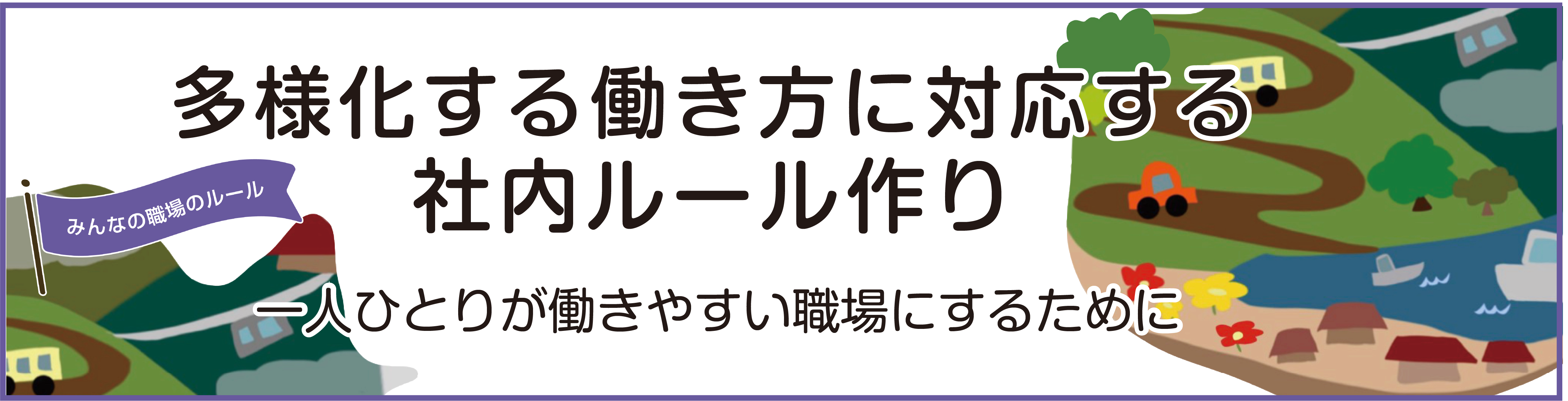働き方改革対応
「働き方改革」にどう取り組むか
今、世界的に「Well-Being」への関心が高まっています。Well-Beingは「幸福」の意味で、身体的・精神的・社会的に健康である状態とされています。Well-Beingが進むと、会社という場で社員一人一人が笑顔でいられる場になり、社員の幸福感にもつながります。
社員一人一人が笑顔でいられるためには、ある程度の多様性を受け入れていく柔軟な組織体制や土壌作りが必要です。
2019年から本格的に動き始めた働き方改革では、過労死などが頻発した反省から「過重労働」や「健康への配慮」に関してより厳しいルールが設けられました。ピラミッド型組織においては、行き過ぎた命令や強制的な労働にならないために、このようなルールを厳格にして運用していくことは重要です。
しかし、「法律でそういうルールになっているから」と一切の変更や例外を認めない、検討しないということになると、組織として柔軟な対応ができなくなってしまいます。そして、それは社員への息苦しさにもつながっていきます。今ある会社のルールで、社員が働きづらさを感じているのであれば、臨機応変に対応できる組織力が必要です。

組織に必要なのは、絶対的なルールではなく、メンバー皆で作り上げてきた文化であり、それを守るために皆が守るべきにある皆が当然のように認識している掟のようなもの、言い換えれば「クレド」なのです。
会社の魅力はその会社しか持ちえない文化の形にあります。その形は対話を通してメンバー皆の生活やそこから生まれる仕事観から形づくられてきます。そしてそれは決して定まった規定ではなく絶えず周りに影響を受けながら変わっていきます。柔軟な対応ができる組織におけるルールは、絶対的な規定や法律とは違い、職場の皆の働きやすさや幸福感に基づいて変化することを前提に対話の中で作られていくべきなのです。
自律分散的な組織運営をしている会社のルールづくりにはある共通点があるように思われます。それは、ルールを作る際にやり方をより具体的に決めたマニュアル的、契約書的なものをつくるのではなく、その制度の趣旨やガイドラインだけを決めて定着させていくということです。「これだけはやってはいけないが、それを守ってもらえればその他は一人一人の判断で自由にやってもらっていい」といった決め方です。
コロナ禍で在宅勤務をせざるを得なくなった会社も多くありました。ほとんどの会社がルールもないままに在宅勤務をスタートさせました。その中でトラブルが起こる会社と、わりとうまく運用する会社がありました。うまく運用できた会社は、最初に基本的なルールを作ったうえで運用しながらコミュニケーションをとり、制度を少しずつ使いやすいものに変えていくということを行っていました。多様な働き方が普通になり、また、その働き方も次々に変化していくこれからの時代のルール作りは、これまでとは全く違ったものとなっていくでしょう。
柔軟な対応ができる組織に変容していくためには、もちろん法令は遵守したうえですが、このような考え方に基づいてのルールづくりが大切です。具体的には以下の3点を抑えておくべきです。
・選択肢を増やす、選べる
・ルールにも趣旨・目的が重要
・フレキシブルに対応
という、大きなポイントが3点あります。
選択肢を増やす、選べる
多様な働き方に対応できるためには、いろいろな選択肢から選べるようにするためのルールが必要です。「テレワークできます」「時短勤務もできますよ」「副業もやっていいですよ」と、さまざまな働き方の推進ができる社内ルールを作っていくべきです。
多様性を認め、新たなルールを作るためには、様々な考えをもつ人たちとのコミュニケーションを取りながら進めていくことも必要でしょう。そうして試行錯誤しながら、多様性を受け入れる土壌を作っていくことが、これからはより大切になっていきます。
「ルールを作る」ことは決して、ルールで働く人をがんじがらめにすることではありません。全くその逆で、先述したように「ルールを作る」ことはより多様で、そして働く方々の選択肢を増やすために必要なことなのです。
ルールにも趣旨、目的が重要
ルールを制定する前には、ルール自体の趣旨や目的をしっかり考えておく必要があります。当たり前のことですが、「流行だからやってみよう」というように、漠然とした理由でルールを制定することは避けましょう。「何を実現したいのか?」「どういうメッセージ性があるのか?」という意思を、ルールに込めて制定しなければいけません。
新型コロナウイルスが流行する前の話ですが、当時ある会社から「テレワークを導入する」という話が出てきました。その会社がテレワークを導入する動機は「あくまでも会社の生産性アップが第一。それを図りつつ社員の働きやすさも目指していく」ということでした。しかし結果としては、社員の働く幅は広がりましたが、一部の社員に業務が集中したことで生産性は落ちてしまったのです。一部の社員には好評であったとしても、会社は「生産性を上げましょう」という趣旨で実施しているので、テレワークで生産性が下がってしまうことが起きてはいけません。このケースでは改めて趣旨を社員に周知して、一部ルールを変更してテレワークを継続しました。
また、テレワークが長期間続いたことにより、人と接する時間が極端に減少し、精神面での不調やストレスを感じている人も少なくありません。テレワークを行う上でのルール決めはもちろん必要ですが、例えば「週に1日はテレワーク勤務の人もオンラインで繋いで、社内メンバーと会話しながら昼食をとる」など、コミュニケーション不足を解消し、テレワークで勤務する社員にも安心感を与えられるルール作りが必要です。
フレキシブルに対応
「常にルールは変わるものだ」という前提で、フレキシブルに対応できるようにしておくことは重要です。とはいえ労働条件に関わることなので、ルールを一度制定してしまうと、そこから不利益変更するには労働者の個別同意が必要になってしまいます。対策としては、以下の流れでテスト導入してみることを推奨します。
- 最初からテスト導入としてルールを制定する
- テスト導入して様子を見る期間を設ける
- 一定の期間内に様子を見て、期間を過ぎたら継続するかどうか話し合う
例えば、全員決まった時間帯に勤務している会社がフレックスタイム制を導入するとしましょう。フレックスタイム制を導入するにあたって「誰もいない時間帯が出てきたときに、電話番はどうするのか?」といった問題も発生します。そういったことも踏まえて解決プランを社内で想定しつつ「まずはいったん、半年間やってみる」とフレキシブルに対応することが必要です。
実際に、「どうしても駄目だったら半年でやめる。継続できると判断した際は本格導入する」という方法で半年間フレックスタイム制を導入した会社もありました。「時間をかけて常に一つのルールを作って、一度ルールを作ったらもうそれ以降は変えない」という感覚ではなく、フレキシブルに「やりたいこと、目的に沿った形で制度を変えていく」姿勢が、今後は重要になっていきます。そういった形で前向きに様々なルールを、フットワークを軽くして作っていこうとする会社姿勢こそが、仕事を苦しく辛いものなのではなく、楽しいこと・幸せなことであると社員に感じてもらうことにつながっていきます。
具体的な就業規則作成ポイント
具体的には、主に以下のようなポイントがあります。
| 内容 | 施行日 | |
|---|---|---|
| ① | 時間外労働の上限規制 | 平成31年4月1日(中小企業 令和2年4月1日)施行 |
| ② | 一定日数の年次有給休暇の確実な取得 | 平成31年4月1日施行 |
| ③ | 労働時間の把握 | 平成31年4月1日施行 |
| ④ | 産業医・産業保健機能の強化 | 平成31年4月1日施行 |
| ⑤ | フレックスタイム制の見直し、高度プロフェッショナル制度の創設 | 平成31年4月1日施行 |
| ⑥ | 均等・均衡規定の整備、待遇に関する説明義務不合理な待遇差を解消するための規定の整備 | 令和2年4月1日(中小企業 令和3年4月1日施行) |
①時間外労働の上限規制
長時間労働を抑制するために、時間外労働(残業時間)の上限が法律により決められました。上限は、原則として月45時間・年360時間とし、 臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。 労使協定を結んでいて、臨時的な特別の事情がある場合は、年6か月まで(1)年720時間以内、(2)2~6か月平均80時間以内(休日労働を含む)、(3) 月100時間未満(休日労働を含む) の範囲内で原則の時間を超えることができます。 なお、自動車運転の業務、建設事業など、一定の業種や業務は猶予、適用除外があります。
②年5日の年次有給休暇の義務付け
10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対して、5日について取得が義務付けられてます。これは正社員だけでなく、一定のパートタイマーも該当しますので、誰が該当するのか、そして5日間は取得できるように管理していくことが必要です。
③労働時間の適切な把握
健康管理の観点から、通常の労働者だけでなく、裁量労働制が適用される社員や管理監督者も含め、すべての人の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務づけられました。労働時間を適切に把握することにより、長時間労働の抑制や健康管理に繋げています。
④産業医・産業保健機能の強化
産業医の選任義務のある労働者が50人以上の事業場は、衛生委員会に対し、産業医が行った労働者の健康管理等に関する勧告の内容等を報告しなければならないこととする。また、産業医に対し産業保健業務を適切に行うために必要な情報を提供しなければならないこととする。といったことにより、健康への配慮が強化されています。
⑤多様な働き方の推進
多様な働き方を推進するための法改正も行われました。フレックスタイムの清算時間が1ヶ月から3ヶ月に拡大されて、例えば、6月・7月・8月の3か月で、6月、7月に長めに働き、8月の労働時間を短くすることで、夏休み中の子どもと過ごす時間を確保しやすくできる。といったことも可能になりました。(ただし、労使協定による定め等が必要です。)また、一定の専門職が「高度プロフェッショナル制度」に該当する場合は、自己の裁量により働くことができるしくみも導入されました。
⑥同一労働同一賃金
パート・アルバイト等のいわゆる非正規社員と正社員との不合理な待遇差をなくすために法律が整備されました。例えば、「均衡待遇規定」として(1)職務内容、(2)職務内容・配置の変更範囲、(3)その他の事情の相違を考慮して不合理な待遇差を禁止。また、「均等待遇規定」として、 (1)職務内容、(2)職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は差別的取扱いが禁止されています。
働き方改革は、健康管理等の面から労働時間を管理するといった事ももちろん必要ですが、一方で、現代の働き方に対応できるように自律的な働き方を後押しする側面も持っています。また、テレワークや副業など、コロナ禍を経てニーズが高まってきた働き方は、会社も社員を信頼して任せる部分が多くなっています。
会社が法律の中で求められる「管理」と社員の「自律」、両方の要素を備えている会社がこれからの組織には必要になっています。そのためには、それぞれの会社ごとに自分たちのやり方に適したルールを作っていくことがより求められていきます。法律のように、「上が決めて守らなくてはいけない」といったことではなく、社員みんなで対話をしながらルールを決めていくことにより、自律性が生まれ、自分たちが作ったルールとして働き方に当事者意識を持つことがこれからの働き方に対応できる組織になっていきます。